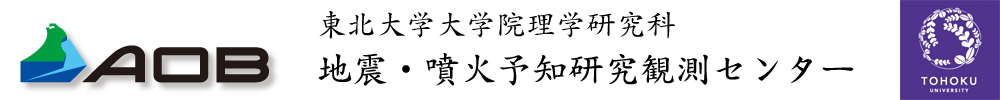機能性流体を用いた誘発地震抑制技術の開発に成功 -地震を起こす断層滑りにブレーキをかける地震抑制技術の黎明-[2025/12/24]
様々な地下開発では、地下に流体を注入する際に断層の応力状態が変化し、微小地震が発生しますが、時に被害を伴う誘発有感地震が発生してしまうことがありました。これまで、注入する流体の量を減らすなどの対策が試みられてきましたが、経済性や技術的な制約があり、抜本的な解決策は見つかっていませんでした。
東北大学流体科学研究所の椋平祐輔准教授、Lu Wang氏(研究当時:流体科学研究所 特任助教)、大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センターの矢部康男准教授、大学院理学研究科地学専攻の澤燦道助教、武藤潤教授の研究グループはせん断増粘流体(STF)を、断層を模擬した粉末に付与し、その摩擦特性を実験的に調べました。その結果、STFを用いると断層の摩擦特性が変化し、断層滑りを安定化させ、地震の発生を抑制できる可能性を示しました。
今回の成果は、STFを使ってより安全な地下資源開発を実現できる他、将来的に地震の抑制技術開発の第一歩となる可能性もあります。
本研究成果は、2025年12月19日付で、米国地球惑星連合の国際学術誌Geophysical Research Lettersに掲載されました。
能登地震、地下の「古マグマ」の破壊が引き金に
3年間継続した群発地震が大地震につながった要因を解明[2025/10/16]
能登半島では、2020年12月頃から活発な群発地震が続いていましたが、2024年元日にマグニチュード7.6の能登半島地震が発生しました。なぜこのような複雑な地震活動が起きたのか、なぜ群発地震が大地震につながったのか、その要因はこれまで不明でした。
東北大学大学院理学研究科の髙木涼太准教授らの研究チームは、高密度な臨時地震観測に基づく高解像度の地下構造探査により、能登半島地震の震源域の地下に、周囲に比べて地震波速度が異常に速い領域(高速度体)が存在することを発見しました。3年前から継続していた群発地震はこの高速度体を避けるように発生したのに対し、能登半島地震の主要な断層破壊はその中で発生しました。この高速度体は、固化した古マグマである可能性が高く、過去の火山活動によって地下に形成された構造とそれによる透水性の不均質が、現在の群発地震の発展や大地震の発生過程を支配した要因であることを示唆しています。
本研究成果は科学誌Science Advancesに2025年10月15日午前2時(米国東部時間。日本時間10月16日午前3時)付で掲載されました。
東北大ー産業技術総合研究所地震系研究者交流会(9/10-11)の報告[2025/9/10-11]
本センターでは,茨城県つくば市の産業技術総合研究所つくばセンターにて,国立研究開発法人・産業技術総合研究所の地震系研究者との研究交流会を9月10日(水)~11日(木)の2日間にわたり開催しました.
現地参加およびオンライン参加を通じて,双方の研究員・教員・技術職員・大学院生が計11件の発表を行い,産業技術総合研究所の活動紹介もいただきながら,今後の連携の可能性について活発な議論が交わされました.
(文責:岡田知己)
2024 年能登半島地震の断層活動を地殻応力場で推定
─ 日本全域での地震発生可能性の評価による、減災への貢献に期待 ─[2025/7/17]
2024年1月1日に発生した能登半島地震に関する以下の論文が掲載され,東北大学においてプレスリリースされましたので,お知らせします。
【発表のポイント】
・2024 年能登半島地震発生前の地震データを用いて地殻応力場を推定し、能登半島地震の断層面のすべりやすさ評価を行なった。
・これまでに提唱されている複数の断層モデルは能登半島地域の地殻応力場に対してすべりやすい状態を示した。
・地殻応力場と断層モデルの両方を用いた断層のすべりやすさ評価を日本全域に適用することで地震発生の可能性評価、地震災害の減災への貢献が期待される。
【論文情報】
タイトル:Evaluation of the favorability of faults to slip: the case of the 2024 Noto Peninsula earthquake
著者:Ayaka Tagami, Tomomi Okada, Martha K. Savage, Calum Chamberlain, Toru Matsuzawa, Ryotaro Fujimura, Kazuya Tateiwa, Keisuke Yoshida, Ryota Takagi, Syuutoku Kimura, Satoshi Hirahara, Taisuke Yamada & Yusaku Ohta
*責任著者:東北大学大学院理学研究科 客員研究者 田上綾香
掲載誌:Earth, Planets and Space
DOI:10.1186/s40623-025-02235-4
URL:https://doi.org/10.1186/s40623-025-02235-4
プレートから上昇する水が巨大地震の破壊拡大を止め、直下型地震を引き起こす? ─ 東日本太平洋側の地震帯の発見が示す地震のメカニズム ─[2025/7/11]
地下深くでプレートから供給され、地表へと上昇する”水”が、巨大なプレート境界地震の広がりを止める一方で、直下型地震を引き起こす可能性があることを明らかにしました。東北大学大学院理学研究科の鈴木琳大郎大学院生(研究当時)と内田直希准教授(研究当時。現在東京大学地震研究所教授)らの研究グループは、深層学習モデルを用いた大量の地震波形解析により、東日本の太平洋沿岸海域〜関東地方下に「前弧地震帯」を発見しました。この地震帯は、従来よりも浅い場所でのプレートからの脱水を示し、そこから上昇する水の経路となっています。深さ約35-75kmのプレートから出た水は、その直上のプレート境界断層を潤滑し、プレート境界巨大地震のすべり域の拡大を抑制する一方、約35kmより浅い地震を活性化させていると考えられます。前弧地震帯は、巨大地震と直下型地震の両方に深く関わる”水みち”であり、将来発生するこれらの地震の姿の予測に向けた重要な手がかりとなります。
本研究成果は日本時間2025年7月11日(金)午前4時に、科学雑誌Scienceのオンライン版に掲載されました。
ICDP-PROTEA国際ワークショップ参加者募集のご案内[2025/6/19]
矢部康男准教授が代表を務める国際陸上科学掘削計画PROTEA(Probing the heart of an earthquake and life in the deep subsurface)の詳細計画を検討する国際ワークショップの対面・オンラインでの参加者を募集します.
開催日:2025年10月16-17日(10月18日にオプションの巡検があります)
会場:Protea Hotel Klerksdorp(南アフリカ)
詳しくは,以下のサイトをご覧ください.
PROTEA, South Africa
東北大学教員が開発にかかわった岩盤工学技術を紹介するワークショップを南アフリカで開催します[2025/6/10]
当センターで開発された岩盤応力測定法(変形率変化法,DRA)をはじめとした、東北大学の教員が開発にかかわった岩盤工学技術(岩盤応力測定法3件、水圧破砕法1件、誘発地震抑制技術1件)を紹介するためワークショップを、岩石力学の国際学会であるAfrirock 2025の関連行事として、岩盤工学技術コンソーシアム(流体科学研究所・伊藤高敏教授が代表、当センター・矢部康男准教授が事務局)と南アフリカの岩盤工学会(South African National Institute of Rock Engineering、SANIRE)が共同して、7月20日にサンシティー(南アフリカ)で開催します。
AFRIROCK GEOTECH WORKSHOP 2025
光ファイバケーブルを活用した海域・地下構造のイメージング手法を開発
─海域における地震波速度構造の詳細把握の実現─[2025/6/9]
近年、光ファイバをセンサーとして振動などを捉えるDASが地震観測などに用いられるようになってきました。この技術は、光ファイバ上を数m〜数十mという超高密度の観測点間隔で約100 kmほどの距離まで観測することが可能です。また、海底に設置されている海底光ケーブルでDAS観測を実施することで、海底における地震動の稠密観測を実現することが可能です。海底での地震動の稠密観測は,地震活動のモニタリングや地下構造のイメージングなど,多目的に応用されるようになってきています。
東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センターの福島駿特任研究員らは、東京大学地震研究所篠原雅尚教授、京都大学防災研究所伊藤喜宏教授と共同で、海底に敷設された光ファイバケーブルを活用した新しい地下構造のイメージング手法を確立しました。広範囲(50-100 km)かつ稠密(約5 m間隔)なデータが取得できることが特長で、得られるDASデータを解析することで、これまでの技術と比べて格段に高い空間分解能で海底下構造を推定できると期待されます。
本研究では、三陸沖に敷設された海底ケーブルを活用したDAS観測により得られた制御震源(注2)を用いた地下構造探査のデータを解析しました。その結果、DASで得られるデータが、海域における地下の構造を詳細に解明する上で有効であることを示すことでき、三陸沖の海域の浅部堆積層内に強い空間的な不均質構造がみられることを明らかにできました。このように地下の地質構造を詳細に把握することができる手法が開発されたことは、地震波の伝播の仕方や地形の成り立ちの理解をはじめとする地球科学的研究のみならず、二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture and Storage :CCS)(注3)などの工学的分野での研究開発にも大きく貢献すると期待されます。
本成果は、5月25日に科学誌Scientific Reportsに掲載されました。
地球内部の水・マグマをとらえ、地震や火山の仕組みに迫る ――地震波と電気伝導度の統合解析による東北地方の地下イメージング――[2025/5/23]
2008年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震に関する以下の論文が掲載され,東京大学・東京科学大学・東北大学・富山大学・産業総合技術研究所・海洋研究開発機構 においてプレスリリースされましたので,お知らせします。
タイトル:Geofluid mapping reveals the connection between magmas, fluids, and earthquakes
著者: Hikaru Iwamori*, Yasuo Ogawa, Tomomi Okada, Tohru Watanabe, Hitomi Nakamura, Tatsu Kuwatani, Kenji Nagata, Atsushi Suzuki, Masahiro Ichiki *責任著者
掲載誌:Communications Earth & Environment
DOI:10.1038/s43247-025-02351-9
URL:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02351-9
【本学研究者情報】
〇大学院理学研究科
地震・噴火予知研究観測センター
教授 岡田 知己(おかだ ともみ)
助教 市來 雅啓(いちき まさひろ)
【発表のポイント】
・地震や火山活動に重要な役割を果たす「地球内部の水・マグマ」の3Dマッピングに成功し、どこにどれだけ存在するのかを、地震、火山、温泉との位置関係とともにイメージングした。
・東北地方中央部の地下40㎞までの領域では、火山・非火山地域を問わずマグマが深部に広く分布すること、またそのマグマから水が放出され、高い流体圧により地震を誘起していることなど、マグマ―水―地震の関連性がはじめて具体的に明らかとなった。
・マグマや水の分布・圧力のマッピングを広域的に展開することで、火山噴火や地震発生のポテンシャル・中長期評価、ひいては減災への貢献が期待される。
【本発表に関係する論文】
Okada, T., Matsuzawa, T., Nakajima, J., Uchida, N., Yamamoto, M., Hori, S., Kono, T., Nakayama, T., Hirahara, S., Hasegawa, A., 2014. Seismic velocity structure in and around the Naruko volcano, NE Japan, and its implications for volcanic and seismic activities. Earth, Planets Sp. 66, 114. https://doi.org/10.1186/1880-5981-66-114
Ogawa, Y., Ichiki, M., Kanda, W., Mishina, M., Asamori, K., 2014. Three-dimensional magnetotelluric imaging of crustal fluids and seismicity around Naruko volcano, NE Japan, Earth, Planets Sp. 66, 158, 2014, https://doi.org/10.1186/s40623-014-0158-y
詳しくは下記をご確認ください。
石川県珠洲市高屋地区 地震観測成果報告会[2025/4/22]
2025年4月22日,東北大学が臨時地震観測点を設置している石川県珠洲市高屋地区において,地震観測成果報告会を行いました。
岡田知己教授,平原 聡・木村 洲徳 両技術職員が参加し,高屋地区の住民の皆さまと,地震観測の現状とこれまで得られた研究成果について活発な議論を行いました。
在日南アフリカ共和国大使館のジェピー公使がセンターを訪問されました.[2025/3/3]
3月3日に,在日南アフリカ共和国大使館のジェピー公使(科学イノベーション教育担当)が当センターに来訪され,当センターの矢部康男准教授,流体科学研究所の伊藤高敏教授と椋平祐輔助教,環境科学研究科坂口清敏准教授との懇談の後,施設見学をされました.
懇談では,矢部准教授が中心となり,7か国14名の研究者が共同で,国際陸上科学掘削計画(International Continental Scientific Drilling Program, ICDP)に提案している,南アフリカでの新たな科学掘削計画PROTEA(Probing the heart of an earthquake and life in the deep subsurface)を紹介しました.また,東北大学をはじめとした日本で開発された岩盤工学技術を南アフリカの大深度金鉱山およびシェールガス開発プロジェクトに実装するためのコンソーシアム構想について説明しました.これらに対して,公使より,「日本と南アフリカの学術および技術交流を通じた,南アフリカの産業振興および次世代の育成に期待する」との趣旨の発言がありました.

施設見学後の記念写真. 左から,坂口准教授,伊藤教授,ジェピー公使,矢部准教授,椋平助教,海田技術職員
日本列島下の全マントル構造とマントル流れ場の高精度推定に成功
―大規模地震や火山噴火の根本理解に一歩―[2025/3/7]
日本とその周辺地域では、複雑なプレート沈み込み帯が形成されており、大規模な地震や火山噴火が頻繁に発生しています。地震や噴火は地下構造と密接に関連していますが、従来の地下構造研究は上部マントル(深さ660 km以浅)に特化したものがほとんどで、下部マントル(深さ660~2889 km)も含めた全マントル構造の詳細な推定を行った研究はありませんでした。
東北大学大学院理学研究科 附属地震・噴火予知研究観測センターの豊国源知助教と趙大鵬教授、高田大輔大学院生(研究当時)の研究グループは、最先端の地下構造推定手法を用いて、本地域下の全マントル3次元構造を初めて高精度で推定しました。この結果、千島弧における巨大噴火は、マントル深部からエネルギー供給を受けて発生している可能性が見いだされました。
またマントルの流れを可視化できる手法を開発し、本地域下の全マントル流れ場も世界で初めて高精度で推定しました。この結果、本地域下に沈み込んだ太平洋プレートが、複数のブロックに分かれて間欠的に下部マントルに沈み込んでいることが明らかとなりました。
本成果は3月1日、米国地球物理学連合(AGU)の科学誌Journal of Geophysical Research: Solid Earthにオンライン掲載されました。